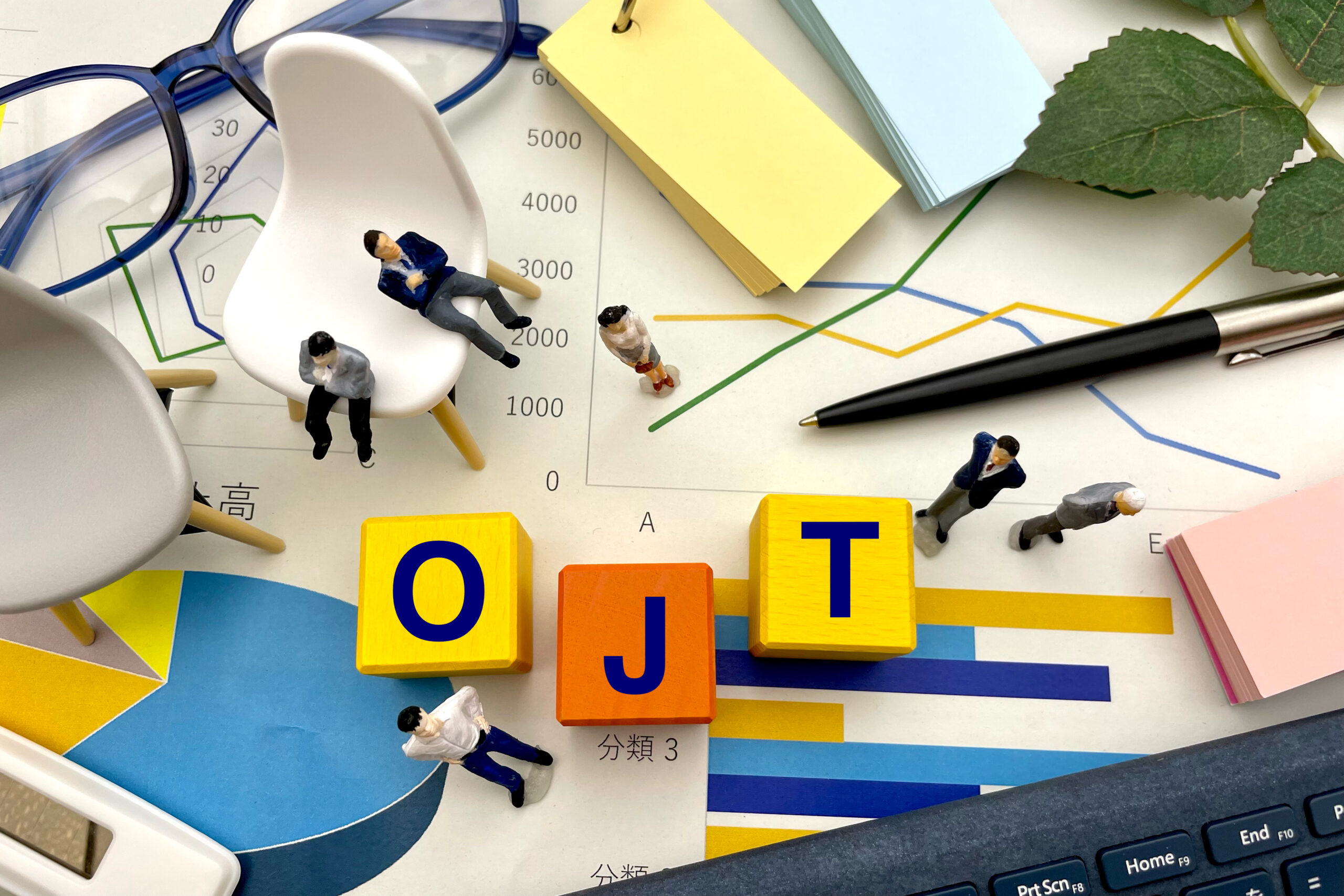
厚労省「能力開発基本調査」で見えたOJTの課題 ― ベアラボが取り組む“教える力”と“関わる力”の再構築 ―
- 株式会社ベアラボ(所在地:東京都新宿区、代表取締役:滝井順子)は、厚生労働省「令和6年度 能力開発基本調査」で明らかになったOJTの実態を踏まえ、現場でOJTがより効果的に機能するための環境づくりと、指導者の育成を目的とした研修の結果を公表いたします。
- OJTが形だけにとどまらず、組織の成長につながる仕組みとして根付くための課題と可能性を示しています。
- ■ 背景
- 厚生労働省「令和6年度 能力開発基本調査」によると、企業の61.1%が計画的なOJTを実施していると回答しています。
- 一見、OJTが広く浸透しているように見えますが、実態は必ずしもそうとは言えません。
- 同調査では、「指導する人材が不足している(59.5%)」「育成を行う時間がない(47.4%)」など、
- 現場における“教える体制”の未整備が依然として課題となっており、OJTが「実施しているつもり」にとどまってしまうケースも多く見られます。
- 実際の現場でも、
- ・初日の業務説明をOJTと呼んでいる
- ・やりたい気持ちはあるが、誰が担当するのか決まらない
- ・忙しくて教える余裕がない
- といった声や様子がうかがえ、OJTの形骸化や属人化が進んでいます。
- こうした状況では、OJTの本来の目的や進め方を十分に理解しないまま実施されてしまうことも多く、その結果、指導の質にばらつきが生じ、新人や若手が成長機会を十分に活かせないリスクも生まれています。
- OJTは単に「現場で教えること」ではなく、計画性・振り返り・関係構築を含めた教育プロセスです。
- OJTを制度として導入するだけでなく、まずはその本質を理解したうえで現場で継続的に実践し、支える体制を整えることが求められています。
- ■ 研修の特徴
- 株式会社ベアラボでは、こうした課題を踏まえ、OJTを「やり方」ではなく「考え方」から理解し直すことを重視した研修を実施しています。
- OJTを「仕組み」として制度化するのではなく、関係性を軸に“理解して続けられる指導”として設計。
- 本研修では、単に教える手順を学ぶだけでなく、「新人・若手をどう理解し、どう関わるか」という「教える力」と「関わる力」の両面を育成します。
- OJTの本質を理解したうえで、日常の中で継続的にOJTを機能させる基盤を整えることを目的としています。
- ■ 研修構成(テキスト内容の一部)
- ・OJTの基本構造:「教える・見せる・やらせる・振り返る」を実践的手法
- ・タイプ別関わり方:思考特性を踏まえた指導スタイルの理解
- ・適切な説明と指示の出し方:相手が理解できる伝え方の工夫
- ・傾聴・質問スキル:相手の主体性やモチベーションを引き出す“聴く力”
- ・報連相を引き出す関係構築:心理的安全性のある関係性づくり
- ・褒め方・叱り方:承認と信頼を軸にした指導姿勢
- ■ 研修結果(事例研究):世代・役割による傾向
- ベアラボが実施したOJTトレーナー研修(複数企業対象)では、ベテラン層(50代以上)と、若年層(20代中心)で、理解度・難易度・受け止め方に違いが見られました。
- 【ベテラン層(50代以上・役職者クラス)】
- 理解度:「十分理解できた」「おおむね理解できた」93%、一方で「あまり理解できなかった」7%。
- 難易度では「高すぎる」と感じた割合が33%。
- 「若手との価値観の違いに戸惑った」
- 「相手の話を聞いているつもりでも、自分の考えを押し付けていたかもしれない」
- 「新しい教え方を理解するのに時間がかかった」
- 「新人社員とのコミュニケーションが苦手だったが、少し自信が持てた」
- 「自己を振り返る良いきっかけとなった」
- 「新人のタイプや思考特性を見極め、早期の独り立ちや定着につなげたい」
- → 経験豊富な層ほど、“これまでの型”を見直しながら学びを実践に結びつける意識が高い。
- 単に知識を吸収するだけでなく、自身の経験を整理し直す「再学習の姿勢」が見られた。
- 【若年層(20代・初めての指導者層)】
- 理解度:「十分理解できた」「おおむね理解できた」89%、「あまり理解できなかった」はなし。
- 難易度では「合っている」「とても合っている」が78%。
- 「新人の頃に感じた不安を思い出し、後輩の立場を意識して関わっていこうと思った」
- 「教える難しさを感じたが、やってみたいと思えた」
- 「報連相や褒め方のコツを実践的に学べた」
- 「相手に合わせているつもりでも、自分視点になっていたことに気づいた」
- 「相手のタイプを踏まえて、関わり方を工夫していきたい」
- → “教える側になる”意識を持ち、前向きに実践を考える姿勢が強い。
- 指導者としての責任感とともに、相手を理解する姿勢が育ち始めている。
- ■ 考察
- 本来、OJTは若手が「後輩に教える」経験を通じて、リーダーシップを育てていく仕組みです。
- しかし現実には、OJTを任せる人材が育っておらず、結果的にベテラン層が担っているケースも多く見られます。これは、個人の問題ではなく、“人を育てる経験の機会を設計できていない”という組織側の人材開発の課題です。
- また、OJTの目的や進め方が十分に共有されないまま実施されるケースも見られます。
- OJTの成果を左右するのは、「誰が、どのような理解のもとで教えるか」という点にあります。
- 今回の結果からは、教える側がOJTの本質を理解し直すことで、現場での指導の質と再現性が高まることが明らかになりました。
- 一方で、年次の高い層ほど、これまでの成功体験や指導スタイルが定着しており、新しい世代に合わせた教え方への切り替えに難しさを感じる傾向があります。
- このことは、OJTを「誰が、どの段階で、どのように担うか」を組織的に設計する重要性を示しています。
- ■ 今後の展開
- ベアラボでは、今回の結果を踏まえ、OJTを「教えるスキル」から「理解して育てる仕組み」へ進化させる取り組みを強化しています。
- OJTは一度きりの指導ではなく、「教える → 振り返る → 続ける」という継続のサイクルの中で定着していくものです。
- そのためには、教える側がOJTの目的とプロセスを理解し、現場で再現できる状態をつくることが欠かせません。
- 教えるとは、単に“点”を伝えることではなく、その点が線となり、面となり、やがて立体的な理解へとつながる道筋を示すこと。
- ベアラボは、OJTを“誰かが教えること”から“組織で育てること”へ。
- 各組織の環境・人材構成に合わせた人材開発の設計支援を通じて、人が育ち、組織も学び続けて成長するサイクルを生み出していきます。
